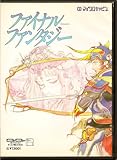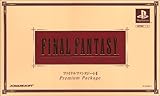| ファイナルファンタジー 発売日:1987年12月18日 機種:ファミリーコンピュータ 価格:5,900円 容量:2M bit ROM |
| 攻略チャート | 武器 | 防具 | 魔法 | 攻略補足・裏技 |
|
関連作品
|
機種
|
発売日
|
備考
|
|
MSX2
|
1989/12/22
|
移植
|
|
|
FC
|
1994/02/27
|
2作収録
|
|
|
WSC/PS
|
2000/12/09
|
2Dリメイク
|
|
|
GBA
|
2004/07/29
|
2Dリメイク
|
|
|
PSP/スマホ
|
2007/04/19
|
2Dリメイク
|
|
|
PS/NS/PC
|
2021/07/29
|
2Dリマスター
|
|
| SOP FFオリジン | PS4/XB/PC | 2022/3/18 | FF1の異説 |
| 特徴 | 世界観 | キャラクター | システム | 開発 |
| 移植版 | リメイク版 | 関連商品 | リンク |
| ■最新情報 (2024/12/18) |
|
発売38周年 NHKで坂口氏やナーシャが出演する特番 当時の企画書原本 堀井氏&坂口氏対談 ・FF1は発売前から気になっていた ・遊んでみて結構バランスがきついなと思った ・DQとアプローチは全く違うが、これはアリだと思った ・画面に凄くこだわっていて、見せるゲームになっていると感じた 現存する唯一のFF1企画書 石井浩一&天野喜孝 対談 前編 公式インタビュー:田中氏 / 石井氏 田中弘道氏インタビュー2018:上/中/下 過去のニュース / FFシリーズ / FFオリジン / ピクセルリマスター |
| ■特徴 |
|
最先端の技術で描かれる革新的なグラフィック 中世ファンタジーにSF要素を融合させた独自の世界観 映画的なオープングや、宇宙にまで手を伸ばすストーリー展開 サイドビューによるフルアニメのバトルシーン フィールド上空を高速に移動できる飛空船が登場 4人パーティ&クラス制、魔法購入&装備システム、階層性MP 大容量の2MbitROMに加え、バッテリーバックアップ採用 開発には外部スタッフとして著名なクリエイターも参加 |
| ■備考 |
|
ファミリーコンピュータ(ファミコン)で発売、50万本を超えるセールスに シリーズ化 本作のヒットにより続編の製作が決定、以降スクウェアの主力タイトルとしてシリーズ化 ストーリーやゲームシステムを前作から引き継がず、毎回全てを一新 移植/リメイク FC版発売の2年後にMSXへの移植版が発売 リメイク版がWSC、PS1、GBA、PSP&スマホで発売 ワンダースワンカラー版はFFシリーズ初のリメイク作品に 本作のリメイクはWSC、GBA、PSPの3回に渡り、グラフィックのリファインが行われている ■セールス FC版 初回出荷本数:40万本 累計販売本数:52万本 発売当時のハードの価格:14,800円(ファミリーコンピュータ) 初回出荷は20万本の予定だったが、40万本に変更 ・任天堂はROMの製造委託において先払い制度を敷いていたため当時のスクウェアにとってはかなり厳しい本数だったが、坂口氏が営業担当を説得 当時のファミコン市場においてFF1やFF2の50万本前後という数字はヒットと呼べるほどではなく、FF3で100万本を超えるヒット作品に ■評価 ファミコン通信クロスレビュー:34/40(8.9.9.8) 全体的に高評価で、特にグラフィックやシナリオへの評価が高い。操作性やバトルのアニメーションを評価する声も。 マイナス意見は少ないが、マニアックであることや、魔法装備システムの複雑さなどが一部指摘されている。 5点や6点が当たり前で9点など滅多に無かった当時のクロスレビューにおいてはかなり高めのスコア。 比較:FF2/35 DQ2/38 ウィザードリィ/33 スクウェア主要ゲームクロスレビュー:33/40(9.9.9.6) FF4発売後に過去に発売されたスクウェアのRPGを同じレビュアーが評価する企画 毛利名人は本作とFF4に9点、FF2とFF3には5点をつけている 比較:FF2/29 FF3/32 FF4/38 読者投票 ファミコン通信 1988年ベストヒットゲーム大賞:3位 ファミマガ ゲーム大賞 1989年:3位 ■他作品への登場 『ディシディアFF』シリーズに光の戦士(WoL)、ガーランド、カオスがプレイアブルキャラとして登場 モンスターハンター(カプコン)に野村氏がデザインしたWoLの防具が登場 『ワールドオブFF』にウォーリアオブライト、セーラ姫が登場 SOP FFオリジン:FF1をモチーフとした新たな物語 ■ボイスキャスト ウォーリアオブライト(DFFシリーズ、他):関俊彦 ガーランド(DFFシリーズ、他):内海賢二 / 石井康嗣 セーラ姫(WOFF):一龍斎春水 |
| ■世界観(ネタバレ注意) |
|
世界観 剣と魔法の中世ファンタジーと、飛空艇やメカなどのSF要素を融合させた、独自の世界観 物語後半では宇宙(ステーション)へ行く機会も(オリジナル版のみ) 世界 人類の他に、ドラゴンやエルフ、ドワーフなどの亜人種が登場 4つのクリスタルの力によって世界は成り立っている。 ガーランドとカオスによるタイムパラドックスによって、輪廻(2000年の周期)の中に閉じ込められている。 クリスタル 地、水、風、火の四大元素を司る存在 輝きが失われると自然が破壊され、世界は混沌に包まれる。 強力なエネルギーを秘めており、4つのクリスタルのパワーを使えば過去の世界にタイムトリップすることも可能 光の戦士 コーネリアの都に現れた主人公。クリスタルに輝きを取り戻すための冒険に旅立つ。 現代(現実世界)から、この世界へと転生(転移)してきたプレイヤー自身。 |
| ■物語 |
|
かつてこの世界は光に包まれ平和だったが、今は混沌に包まれている。 人々は伝説に伝わる光の戦士が現れるのを願い続けてきた。 そしてついにコーネリアの都に光を失ったクリスタルを持つ4人の戦士が現れた。 戦士たちはクリスタルに輝きを取り戻すため、広大な世界のどこかに存在するクリスタルの祭壇を求めて旅立つ。 |
| ■主要キャラクター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ■ゲームシステム |
|
■キャラクター パーティ 4人固定。ゲームスタート時に4人分の名前を入力、職業を選択 クラスチェンジ ゲーム中盤のイベント後、対応した上位職に自動転職 グラフィックが2頭身から3頭身に変化 より強力な武器や魔法が使用可能に レベル バトルで取得した経験値が一定量貯まるとレベルアップ、各ステータスが上昇 レベルの上限は50 装備 武器は全40種。攻撃力と命中率の概念がある。 防具は鎧、盾、兜、手の4箇所で、全40種。防御力の他、重量の概念も。 魔法 白魔法(回復系)、黒魔法(攻撃系)の2系統 各魔法は威力や性能に応じて1~8までのレベルに分類され、1つのレベルに4種類の魔法が存在 魔法は街の魔法屋で購入することで修得。1つのレベルに3つまで修得可能 キャラクターのクラスによって使用可能な系統やレベルが異なる。 魔法の使用可能回数はレベル毎に分かれており、高レベルの魔法ほど使用可能回数は少ない。 ■フィールド ワールドマップ プレイヤーキャラクターを操作して広大な2Dフィールドを移動(ウルティマ方式) 街やダンジョンなどのシンボルに重なると別マップへ切り替わる。 移動中は一定確率でバトルが発生(ランダムエンカウント) 物語後半は飛空艇により、フィールド上をストレスなく自由に移動可能 街・城 世界の各地に存在する。エリア内ではエンカウントしない。 NPCとの会話による情報収集や、店で装備や魔法を購入することが可能 ダンジョン ワールドマップ上よりも強い敵が出現。最深部にはボスが待ち受けていることも。 宝箱が置かれていることもあり、開けるとアイテムが手に入る。 ■乗り物 カヌー 入手すると川や湖の上を移動できるようになる。 船 海上を2倍速で移動することができる。港からのみ上陸が可能。 飛空船 フィールド上空を4倍速&エンカウント無しで移動。着地可能場所は平原のみ。 本作を代表する要素の一つで、後のFFシリーズにも受け継がれた。 ■ユーザーインターフェース ボタンひとつで「話す」や「調べる」などが即座に行える単純明快な操作(ドラクエのようにメニューを開いてコマンドを選ぶ必要がない) 戦闘画面のメッセージスピードが変更可能(8段階) ■セーブ バッテリーバックアップにより、進行状況のセーブ(保存)&ロード(再開)が可能(セーブ枠は1箇所のみ) セーブは町の宿屋で行えるほか、ワールドマップ上で寝袋、テント、コテージを使用することでも可能 バトルで全滅するとゲームオーバーだが、セーブした場所からすぐに再開できる バッテリーバックアップ ・ROMカセット内に搭載されているSRAMに少量のデータを保存しておく技術。本体の電源を切ってもデータが消えない。 ・内蔵電池が寿命(数年)を迎えるとデータは消失するようになる。 |
| ■その他 |
|
プレイヤーキャラクター(4人) ゲーム開始時に4人分の名前を入力&ジョブを選択 性格付けなどはなく、一切喋らない。また、特定の一人が主人公ということもない。 プレイヤー自身が本作の世界に転生し、エンディングで元の世界に帰還するという設定 オープニング オープニングシーンは映画的で、ゲームスタート時ではなく、物語序盤の途中(後述の展開後)で発生 王様から依頼を受け、ボスを倒して姫を救出するという、通常の物語であれば終わりを迎えるような内容をプロローグ的な位置付けにすることで、壮大な物語の始まりを演出 BGM FCの音源は3音(+効果音)だが、FF1~3は2音でメロディを流し、1音をエコーパートにすることで、表情豊かな音楽を作り出している(作曲環境はMSX) バトルBGMは1曲のみで、ボス専用の曲は存在しない。 “プレリュード”と“オープニングテーマ”はFFを象徴するBGMとして後のシリーズに受け継がれた。 ミニゲーム 隠し要素として「15パズル」がプレイ可能 本作がRPGにおいて初めてミニゲームを採用したタイトルに デスマシーン 特定の場所&低確率でエンカウントする、ラスボスに勝るとも劣らない強さを持つ強敵(隠しボス的な存在) 核攻撃を行ってくるメカで、後に魔界塔士サガにも登場 その他 スタッフロールはエンディングではなくオープニングで流れる 敵キャラ128種、武器40種、防具40種、魔法64種 初期ロットには不具合があり、注意書きがパッケージに封入 北米版 1990年に任天堂から発売 国内版とは異なるパッケージで、84ページの説明書やダンジョンマップなどが同梱 |
| ■仕様 |
|
容量:2Mbit*ROM + 64KbitSRAM バッテリーバックアップ(セーブ枠:1箇所) 品番:SQF-FF 定価:5,900円(税別) 平均クリア時間:約20時間 *2Mbit = 256kb/0.25MB ROM容量比較 1M:ドラクエ2 / サガ1 2M:FF1 / FF2 / ドラクエ3 / サガ2 4M:FF3 / ドラクエ4 |
| ■開発 | |||||||||||||||||||||||||||
|
■開発 開発期間は半年弱、開発人数は約6名 坂口氏が率いるスクウェアAチームが開発(Bチームは田中氏、Cチームは青木氏?) 開発は当初3~4人でスタート、6人が中心となって開発、最終的に関わった総人数は20名近くに DQに触発された坂口氏からRPGを企画するよう指示を受けた石井氏が世界観などの基盤を立案 グラフィックを最も重視して開発 開発途中で行き詰まり、RPGの制作経験を持つ田中氏が合流し、システム全般を構築 ゲームデザインは彼らが学生時代に熱中したウィザードリィやウルティマからの影響が強い チームの規模や制作コストも含めスクウェア過去最大のプロジェクトに タイトルの由来 “語感の良い同じアルファベットの繰り返し”ということで『FF』(エフエフ)という略称が『ファイナルファンタジー』というタイトルより先に決定 当初は「ファイティングファンタジー」の予定だったが、同名のボードゲームが存在したため変更 かつて坂口氏は「“これが売れなければゲーム業界から足を洗う”という決意を込めた」と発言していたが、後に「Fで始まる単語ならなんでも良かった」と後付であったことを暴露 グラフィック プログラマーの高度なテクニックとアイデアにより、革新的なグラフィックを実現 メモリの効率化によりグラフィックに多くを割り当てており、地形パターンに斜めのタイルを入れることで、角張りのない滑らかで美しいフィールドに 石井氏は(既存のRPGでは茶色や灰色だった)岩肌を白くすることでファンタジーの世界を表現 オープニングの一枚絵や街のマップは渋谷氏が制作、屋根のある家が並ぶリアルな町並みに シナリオ 河津氏と石井氏が基本構造を1日で構築、それを元に坂口氏が執筆 タイムトリップはプログラマーの岡部氏によるアイデア 世界観 RPGといえば中世ファンタジーだった時代に、SF要素を織り交ぜた世界観はインパクトが強く、後のFFの伝統となっていった。 「僕らは元々、剣と魔法の王道ファンタジーに浸かっていた人間ではないので、別にファンタジーに機械があってもいいと思っている」(坂口氏) ゲームシステム 田中氏がバトル以外のほぼ全てのシステムを構築 バトルは河津氏が製作、サイドビューは石井氏のアイデア 田中氏による経験値テーブルはFF3や聖剣2・3、ゼノギアスまで継続使用 プログラム フィールド画面のスクロールとダンジョンなどのマップ画面は海外プログラマーのナーシャが担当 ・同氏はApple IIでの開発経験がありファミコンのCPU(6502)を熟知していたため、マニュアルにはない独自の手法でハードのスペックを引き出し、飛空船の高速スクロールなどを実現(開発段階では16倍速も) バトルは日本側のプログラマー(吉井氏)が全面的に開発 表示系以外のゲーム部分は田中氏の仕様書どおりにプログラミング 隠し要素の「15パズル」はナーシャが独断で実装 ROM容量 発売当時としては最大サイズの2メガビットROM(0.25MB)を採用 ・容量のほとんどをグラフィックに使用 以降FFシリーズは常にその時点での最大容量のROMで発売 また、ドラクエに先駆けバッテリーバックアップを採用 キャラクター&モンスターデザイン キャラクターは石井氏が元のデザインを起こし、それを元に渋谷氏がドット絵を制作 イメージイラストを依頼された天野氏は北欧神話、ギリシャ神話、アーサー王の世界観をイメージして製作 モンスターグラフィックは渋谷氏や時田氏が制作 ・キーモンスターは天野氏の原画を元にデザイン、その他のモンスターは天野タッチを意識して新たにデザイン BGM 当時スクウェアの正社員の中で唯一の作曲家だった植松氏が担当 (バロック調のDQに対し)現代的に、メロディアスにというアプローチで作曲 プレリュードはマスターアップ直前に30分で製作 外部スタッフ 鳥山明やすぎやまこういちなどの著名人を集めたドラゴンクエストへの対抗心から、本作も複数人の外部クリエイターを起用し広報戦略においてアピール 天野氏にイメージイラストを描いてもらうことを最初に提案したのは石井氏で、世界観を構築する際にも影響を受けている スタッフロールは外部スタッフのみ名前が表示され、社内スタッフは“スクウェアAチーム”とだけ表記(後のWSC版で初めてオリジナル版の内部スタッフが判明) 大作主義 スクウェアが設立当初から掲げていたスタイル(ハイリスク・ハイリターン) クリエイターに豊かな開発環境を提供し、開発費や宣伝費を惜しみなく投入 制作費は7000~8000万、広告費などを含めると1億5千万以上に 広報 天野氏によるファンタジーアートを全面的にアピール 坂口ディレクター自ら雑誌社を渡り歩き、営業・プロモーションを展開 発売前は無名で注目度が低く、ページを割いて大きく取り上げたのはファミコン通信(現・週間ファミ通)のみ ・このファミ通の特集記事とクロスレビューが本作のヒットに大きく貢献 「DQの対抗馬になるようなゲームは扱えない」と門前払いを喰らったことも キャッチコピー(雑誌広告) 未知なる国から、伝説のRPG 伝説のRPGがベールを脱ぐとき、君はクリスタルの戦士に生まれ変わる。 スクウェアは本作の前に『聖剣伝説』というタイトルを2度に渡り開発していたが、どちらも発売中止に 本作の完成後スタッフは“中山美穂のトキメキハイスクール”の開発に携わり、その後FF2の制作を開始 ■ドラゴンクエストとの相違点 当時大ヒットしたドラゴンクエスト(DQ)に対抗意識を持って製作、差別化を図りつつも独自性を強調 FF1発売時、DQは2までが発売済み(FF1のROM容量はDQ3と同等) DQは続編においてストーリーやゲームシステムを前作から引き継いだのに対し、FFはどちらも一新 (DQに先駆けて)昼夜の要素も企画されていたが、諸事情により見送られた。 DQの産みの親である堀井氏も「DQ5ぐらいまではFFを意識(ライバル視)していた」と発言。坂口氏&堀井氏によると、FF6&DQ6以降は異なる方向性に進んだためお互い意識しなくなったとのこと ドラクエ(1~4)がROMカセットの色を「黒」で統一していたのに対し、FF(1~3)は「白」で統一
■影響 当時日本ではDQ1とDQ2のヒットによりRPGブームが到来しつつあり、各社からDQのクローン作品が幾つか登場し始めていたが、本作はDQとは大きく差別化が図られており、中でもグラフィックはDQを上回る美しさであったため、当時のゲーマーに大きなインパクトを与え話題となった。 一方で独特なゲームシステムや荒削りなゲームバランスによる敷居の高さも相まって、DQに比べるとややマニア向けのRPGとして認知されつつも、FF2、FF3と経て徐々に人気が上昇。 SFC移行後のFF4からはシステムやバランスが整備され、DQとは異なるストーリー主導型のRPGとして、その地位を確立。セールス・評価ともにDQに並び称されるほどのRPGへと成長していった。 ■リメイク FFシリーズは「リメイクに時間をかけるよりも新作の開発を優先したい」という坂口氏の意向により基本的にベタ移植しか行われていなかったが、本作で初のリメイクが行われた。 これまでFFシリーズ(ナンバリング)は据置機で発売されてきたが、本作のリメイクにおいて初めて携帯機で発売 バンダイが開発した携帯ゲーム機初のカラー対応ハード「ワンダースワンカラー(WSC)」で発売 ・当時はゲームボーイの後継機種GBAも登場予定だったが、スクウェアは任天堂から参入を拒否されていた WSC本体の販売に大きく貢献(WSCを牽引したのはスクウェアのみで、スクエニがGBAへ参入後は一気に衰退) 一部内容の変更 オリジナル版では宇宙ステーションだった「浮遊城」が、ラピュタのような上空に浮かぶ城に ・この変更により、EDなどでも語られている「宇宙にまで手を伸ばした文明」と齟齬が発生 |
| ■メイン開発スタッフ(敬称略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※FF1~3発売当時のインタビューでは坂口氏の役職はプロデューサーで、田中氏がディレクターとなっている |
| ■関連情報 |
|
JRPG創世期 1970年代 米国でD&Dの影響を受けたダンジョン探索ゲームが登場 1981年 米国でウルティマ、ウィザードリィなどのRPGが発売 1984年 国産RPG「夢幻の心臓」発売 1985年11月 ザナドゥ発売 1986年2月21日 「ゼルダの伝説」発売 1986年5月27日 ドラクエ1発売 1987年1月14日 リンクの冒険(アクションRPG)発売 1987年1月26日 ドラクエ2発売 1987年6月30日 未来神話ジャーヴァス発売(FC初のバックアップRAM搭載) 1987年9月11日 「デジタルデビル物語 女神転生」発売 1987年10月 各社からドラクエ風RPGが9タイトル発売(桃太郎伝説など) 1987年12月18日 FF1発売 1988年2月10日 ドラクエ3発売 1988年12月17日 FF2発売 |
| ■MSX版 | |||
ファミリーコンピュータ版からの移植 FM音源に対応、サウンドが強化 媒体がフロッピーディスクなのでロードは遅い ハードの仕様上、画面のスクロールはコマ送りのように動く ・MSXはハードウェアスクロール機能を備えていないため 動画 (YouTube) |
| ■ファイナルファンタジー I・II | |||
FC版のFF1とFF2が一つのソフトに収録 攻略本が付属 誤字などの不具合が一部修正 ファミコン通信クロスレビュー:26/40(8.7.6.5) 備考 FF6の約1ヶ月前に発売 ニューファミコン(1993年12月1日発売)向けに投入(TVCM) 全FCソフトの中でも最後から3番目に発売 |
| ■WSC版 | ||||
ベタ移植ではなく、FF初のリメイク作品 携帯ゲーム機『ワンダースワンカラー』で発売(本体と同時発売) シナリオに大きな変更は加えられていないが、演出等は大幅に強化
グラフィックは大幅に強化され、SFC後期のFF並に ・オリジナル版ではSFだった浮遊城が、本作以降のリメイクではファンタジーに システムの見直し(エンカウント率の修正やダッシュ機能の追加など) サウンドも大幅に進化、ボスバトルBGMが複数追加 国内販売本数:51万本(本体同梱版含む) 開発:トーセ ワンダースワンカラー本体同梱版 定価:9,999円 特製カラーのWSC本体とゲームソフトのセット 割安な価格設定(但し実売価格はほぼ定価) |
| ■PS版(PS/PSP/PS3) | ||||||
|
ファイナルファンタジー
ベースはワンダースワンカラー版 オープニングムービーが追加、イベントシーン・演出多数追加、メッセージに漢字を使用 ノーマルモードに加え、難易度が大幅に下げられたイージーモードが追加 メモファイル(簡易セーブ)機能追加 モンスター図鑑、天野喜孝アートギャラリーなどを搭載 魔法は店で購入するとすぐに覚えられるように変更 サウンドは大幅にクオリティアップ(アレンジ:関戸剛) 国内販売本数:20万本(プレミアム版は除く) ファイナルファンタジーI・II プレミアムパッケージ
FF1+FF2のセット 天野喜孝ピクチャーレーベル フィギュア3体同梱 ゲームアーカイブス 配信開始日:2009年6月24日 価格:600円(税込) |
| ■フィーチャーフォン版 |
|
対応機種:携帯電話(iモード他) 発売日:2004年3月1日 価格:500円(税込525円)/月 WSC版同様オリジナル版の移植で、携帯電話向けにグラフィックをリニューアル P900i&P900iVにプリインストール、その他の機種へは月額500円で配信 2018年3月31日をもってアプリの配信元であるFFモバイルと共にサービス終了 |
| ■GBA版 | |||
|
ファイナルファンタジーI・II アドバンス
■変更点 魔法は回数制からMP制に変更(FFI) アイテムは装備しなくても使用可能に(FFII) LRボタン同時押しで戦闘離脱 コンフィグ画面やインターフェイスを統一化 Bボタンダッシュ追加 どこでもセーブが可能 テキストは漢字と平仮名の選択が可能 会話シーンではキャラクターの顔グラフィックが表示 モンスター図鑑、ミュージックプレイヤー追加 ■FFI エクストラダンジョン「ソウル・オブ・カオス」 新ダンジョンは4つで、自動生成型 条件を満たすと封印されていた入り口が開く I・II以外のアイテムやモンスターが登場 ■FFII エクストラストーリー「ソウル・オブ・リバース」 物語の中で儚く散っていった仲間達の魂が繰り広げる物語 主人公達がラストダンジョンに潜る裏で、同時に彼らが戦っていたという設定 ■製作スタッフ プロデューサー:時田貴司 開発:トーセ / スクウェア・エニックス第7開発事業部 ■その他 国内販売本数:29万本 ファミ通クロスレビュー:35/40 クラブニンテンドーがFF1の「ストラッププレゼントキャンペーン」を実施 |
| ■PSP / 旧スマホ | |||
FF生誕20周年企画・第一弾 グラフィック完全リニューアル リメイク版をベースに新要素が追加 後にスマートフォンでも配信 グラフィック 画面サイズはGBA版の2倍に、グラフィックもシネスコサイズ、高解像度用にすべて一新 町では光と影の表現や、雲の陰が流れる演出なども追加 フィールド画面はFF6のような奥行きのある表現を採用 PS版のOPムービーをPSPの映像再生能力に合わせ再収録 サウンド サウンドは移植版の中でも過去最高音質で収録(アレンジはGBA版と同一) FFシリーズ歴代ボスとのバトルは、該当BGMのアレンジバージョン 追加要素 ゲーム内容はGBA版に準拠 GBA版の追加シナリオ「ソウル・オブ・カオス」を完全収録 PSP版オリジナル要素として、新ダンジョン「時の迷宮」が追加 モンスター図鑑、ミュージックプレイヤーに加え、新たに「天野喜孝ギャラリー」が追加 当時のイラストやデザイン画、描き下ろし最新作まで網羅 ゲームの進行と連動して開放 テキストはひらがなと漢字に加え、英語も選択可能 アルティメットヒッツ(廉価版) 発売日:2009年7月30日 価格:2,940円 公式ガイドブック ■スマートフォン版 対応機種:iOS / Android / Windows Phone 配信日:2010年2月25日(iOS) / 2011年12月1日(Android) 配信価格:800円 PSP版からの移植(追加要素なども全て収録) UI(操作)はスマホ向けに最適化 ピクセルリマスター版の発売に伴い配信終了 |
| ■関連商品 | |
|
■オリジナル・サウンドトラック (FC版)ファイナルファンタジーI・II 全曲集:Amazon 全49曲 作曲:植松伸夫 オリコン初登場4位 FF1&FF2の全楽曲を収録したFFシリーズ初のオリジナルサウンドトラック メドレータイプのアレンジ曲(2曲)、FF2未使用曲(4曲)も収録 モノラルの原曲(FCはステレオ非対応)を、高音と低音を左右に分けることで擬似的にステレオ化 ・(DQのサントラのように)ステレオ楽曲に再構築されているわけではないので、ヘッドホン等で聴くと違和感が非常に強い アレンジバージョン1はプレリュード、オープニングテーマ(FF1)、メインテーマ(FF2)、マトーヤの洞窟(FF1) アレンジバージョン2はカオス神殿(FF1)、戦闘シーン2(FF2)、街(FF1)、フィナーレ(FF2) PS版 FF I・II オリジナルサウンドトラック 36+29曲 2枚組 編曲:関戸剛 監修:植松伸夫 オリコン初登場87位 初回盤:特殊パッケージ 楽曲はWSC版(サントラ未発売)がベース(WSC版同様関戸氏がアレンジ) 追加楽曲は関戸氏が既存楽曲のモチーフを引用して作曲 他の移植&リメイク版も基本的にPS版のBGMに準拠(ただしPSP版以降に追加された歴代FFボス戦のアレンジBGMは未収録) FINAL FANTASY I.II.III Original Soundtrack Revival Disc 2018年8月15日発売:楽天 / Amazon ・映像付きサントラ(BDM) ・ファミコン版FF1~3の全楽曲を収録(90曲以上) ・mp3ファイル同梱 アレンジアルバム 交響組曲 ファイナルファンタジー (SYMPHONIC SUITE FF) 全7章/14曲 オーケストラ(ライブレコーディング) 演奏:東京交響楽団 編曲:服部克久・服部隆之 1989年5月20日五反田の簡易保険ホールで行われたコンサートを収録 FF1からは「プレリュード」「オープニング」「街」「マトーヤの洞窟」「メインテーマ」「カオスの神殿」「グルグ火山」を収録 PIANO OPERA FF I / II / III 植松氏監修によるピアノ・アレンジアルバム Distant Worlds music from FF 「FFI~IIIメドレー2002」収録 FF バトルアレンジ -THE BLACK MAGES- FFI「バトルテーマ」収録 THE BLACK MAGES II -The Skies Above- FFI「マトーヤの洞窟」収録 ディシディアFF オリジナルサウンドトラック 「メインテーマ」「戦闘シーン」「ダンジョン」(全てアレンジバージョン)収録 Distant Worlds IV: more music from FF フルオーケストラ演奏による新録音源 FF1~FF15の中で人気の高い15曲を収録 ファイナルファンタジーV 5+1 / F.F.MIX 「マトーヤの洞窟」をSFC音源で再現したアレンジバージョンが収録 ■攻略本 FC版攻略本 FF完全攻略本 発行:徳間書店 編集:ファミマガ編集部 キャラ紹介、各種データ、マップ、攻略情報 FFI・II 完全攻略編 発行&編集:NTT出版 制作協力:スクウェア 各種データ、マップ、攻略情報(ラスボスまで掲載) PS版攻略本 ファイナルイシュー FF1・2 公式コンプリートガイド WSC版攻略本 Traveler's Guide 公式コンプリートガイド Vジャンプによる攻略本 GBA:公式コンプリートガイド GBA:Vジャンプによる攻略本 PSP:公式ガイドブック ■書籍 小説 ファミコン冒険ブック FF 勇者に光りあれ! ゲームブック FF クリスタル継承伝説 楽譜 FF1・2・3全曲集 楽しいバイエル併用 FF1 ピアノソロ 原曲に近いアレンジシリーズ 設定資料 FF20thアニバーサリーアルティマニア:File1:キャラクター編 / File2:シナリオ編 / File3:バトル編 ■その他 フィギュア FFTA改mini 光の戦士 FF VARIANT PA改 ヒーロー オブ ライト DVD 『FINAL FANTASY:THE ADVENTURE BIBLE』 |
| ■リンク |
|
記事 36周年記事 FF35周年:GW / ファミ通 現存する唯一のFF1企画書 『FF』はどのように世界に広がっていったのか? (ファミ通) 坂口博信氏特別講演レポート (4Gamer) インタビュー 石井浩一&天野喜孝 対談 前編 動画:天野氏&渋谷氏インタビュー 公式インタビュー:田中氏 / 石井氏 田中弘道氏インタビュー(2018年):上 / 中 / 下 『聖剣伝説』開発者トーク (4Gamer) 『聖剣伝説』歴代開発陣インタビュー (4Gamer) 植松伸夫が語るスクウェア初期作品の思い出 天野喜孝氏インタビュー (withnews) 坂口博信氏インタビュー (niconico) テラバトル:坂口博信氏インタビュー (ファミ通) 石井浩一氏インタビュー (4Gamer) スクエニのデザイナー・渋谷員子氏にインタビュー (4Gamer) 社長が訊く『ラストストーリー』坂口博信/植松伸夫 (任天堂) 社長が訊く『FFCCクリスタルベアラー』河津秋敏 (任天堂) iPhone/iPod touch版FF1・FF2製作者インタビュー (Gpara) GBA版 時田氏インタビュー 映像 FF1&2セット版TVCM (YouTube) NHK特番 NHK国際放送:FF1誕生秘話(英語) NHKレジェンドゲームヒストリーFF回(日本語版) BSP4K:2024年12月30日(月)午後10:30~11:15 BS:2025年1月3日(金)午後10:30~11:15 日本語版は拡大パートにナーシャが出演 |